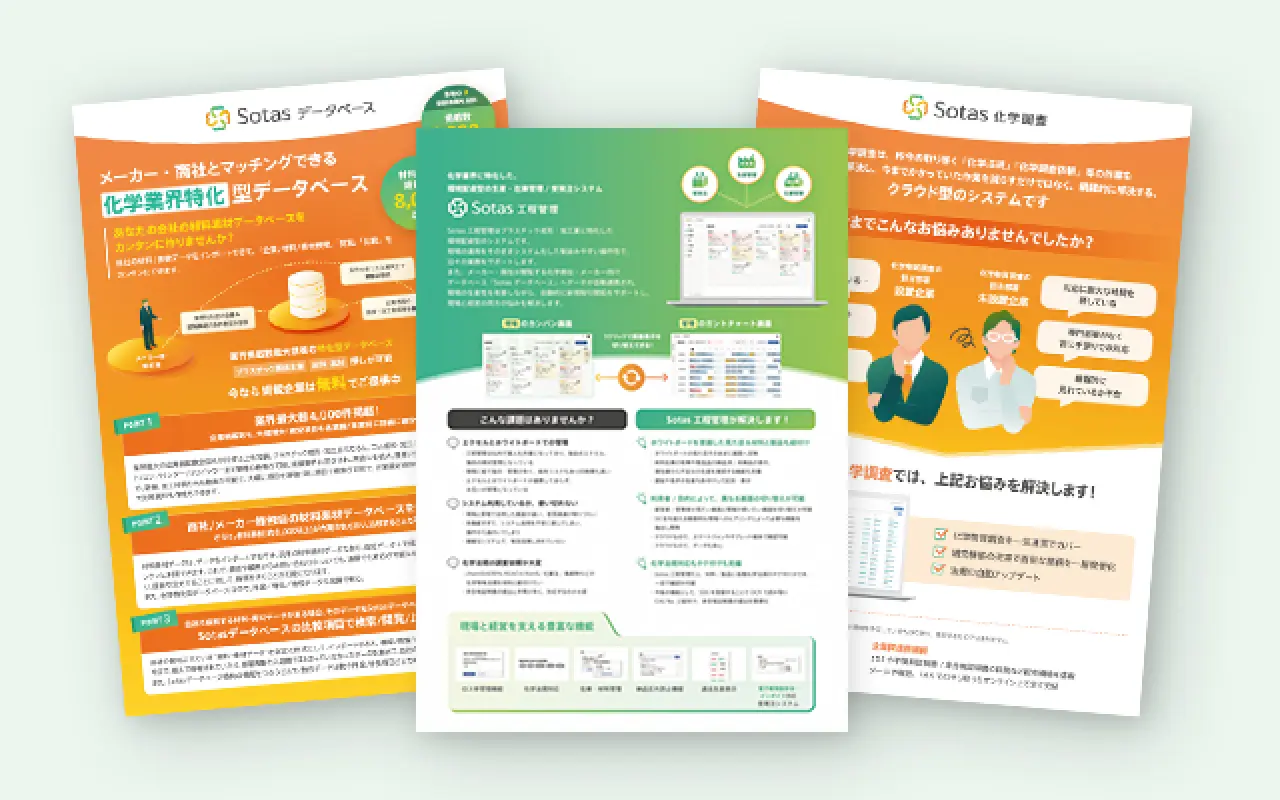- 企業概要
- 塩ビ管・継手、ポリオレフィン管・継手および関連製品の製造、販売
- 企業規模
- 300名-1,000名
クボタケミックスでは、研究開発部門に蓄積された材料データや知見を継続活用できる仕組みとして、整理・共有するとともに、研究者が安心して判断できる環境を整え、環境安全部や製造現場まで含めた安全性を高めるために、Sotas化学調査とSotasデータベースを導入されました。
研究の信頼性と安全性を両立し、“誠実なものづくりを仕組みで支える”という共通の理念のもとで運用が進められています。その研究開発の最前線で、“製造者としての誠実さ”を追求するのが、材料研究部 材料基盤強化グループの松尾祐奈さん。聞き手は、Sotas代表の吉元裕樹が務めました。
すべての材料に、理由を持つ。誠実を“確かさ”で支える。
吉元(Sotas):まずは、松尾さんの部署の役割について教えてください。
松尾さん(クボタケミックス):私の所属する材料研究部では、社内で扱うすべての材料情報を統括しています。材料の物性データや成分情報を管理しながら、法規制対応や安全性評価も行っています。単に研究だけでなく、会社の知識としてどう財産化するかという視点を常に持っています。
吉元:ものづくりの現場では、どのような課題を感じていますか?
松尾さん:私たちが扱う水道管は、一度施工すれば50年もつ素材です。言い換えれば、一度つくったものが長期間社会に残り続ける。だからこそ、“今つくるもの”の品質や信頼性が将来の社会に直結します。
昔のように「物を作れば売れる」時代ではありません。環境対応や安全性、トレーサビリティなど、企業としての責任がますます重くなっています。
吉元:私が松尾さんのお話を伺っていて印象的だったのは、材料について徹底的に調査し、必要な書類を一つひとつ丁寧に確認されていることでした。
ここまで厳重に管理されているのは、まさに製造者としての誠実さだと感じました。
松尾さん:ありがとうございます。材料の情報は、最終製品の品質にも、現場の安全にも直結します。“自分が確認したものを信頼できるようにする”という意識で取り組んでいます。
理想を形にする、“仕組み”との出会い。
吉元:Sotasを知ったきっかけは?
松尾さん:展示会ですね。初めて見たのはSotasデータベースでした。そのとき、「自分たちの理想が叶うかもしれない」と直感しました。それまで使っていたツールでは、思い描いた管理の形を再現するのが難しかったんです。
一方、Sotasデータベースでは、社内の研究データやTDS情報を体系的に整理し、必要な情報を自分たちで追加・更新していける。つまり、“自分たちの研究スタイルに合わせて育てていける仕組み”だと感じました。
「頭の中の整理の仕方を、そのままシステムで再現できる」――そんな印象を受けました。研究データを“使える形”で残せることに、強く惹かれました。
その後に知ったのが、Sotas化学調査でした。こちらはNITE CHRIPをはじめとした各種法令情報と常時連携し、最新の法規制情報と当社の材料データを自動で突合することができる、これなら法規制対応やSDSの管理もより正確かつ効率的に進められる。「これは自分たちの業務にも活かせそうだ」と感じました。
吉元:導入までの道のりはいかがでしたか?
松尾さん:初期設定には2〜3か月かかりました。データベースに“会社の頭脳”とも言える情報を入れることになるので、セキュリティ面や社内基準とのすり合わせは、特に慎重に進めました。当社の運用には厳密なセキュリティ条件があり、一般的なクラウドサービスでは適合が難しい部分もありましたが、Sotasさんが真摯に対応してくれたことで導入を前に進めることができました。
正しさを積み重ね、信頼を育てる。
吉元:クボタケミックスさんは、もともとSDSや材料データの管理体制がとても整っている印象があります。
そのため導入までのプロセスも非常にスムーズで、初期段階から明確な方針を持たれていたのが印象的でした。
今はどんな意識で運用を進めていらっしゃいますか?
松尾さん:今後はまず、データを正しく保ち続けることを自分たちの基準としていきたいと考えています。
データが古い可能性があれば、そこから生まれる判断の信頼性も揺らいでしまう。そうなると、自分たちの研究の“誠実さ”まで曖昧になってしまう気がしてしまうんです。
“正確な状態で整理し、常に最新にしておくこと”――研究者としても、製造事業者としても、この状態を当たり前にしていきたいんです。
その意識のもとで、少しずつデータを整えながら、自分たちの手で“生きた知識”にしていく作業を進めています。
進化を、自分たちの手でデザインする。
吉元:松尾さんは、とても“徹底的にやる”タイプでありながら、新しい技術やツールにも積極的ですよね。そのバランスがすごく印象的です。
松尾さん:はい。新しいものはどんどん試したいタイプなんです(笑)。
実は別のツールも検討していましたが、Sotasのプロダクトは圧倒的に見やすい。それに加えて、ブラッシュアップのスピードが速く、驚いています。
改善の早さ、質問させて頂いた際の回答の早さに、“使う人に寄り添ってくれる”仕組みだと感じています。
吉元:今後、Sotasをどのように活用していきたいと考えていますか?
松尾さん:将来的には、社外への窓口である営業メンバーが直接Sotasを見て、問い合わせにその場で対応できるような状況をつくれたらと考えています。
そうなれば、会社としての信頼もさらに高まり、営業メンバーや私たち研究開発メンバーも本業に集中できるはずです。
また、現場での安全教育にも活かせるようにしたいと思っています。今は必要な書類を紙で回して確認していますが、Sotas上でそれを代替できれば、よりスムーズに正しい情報を共有できる。「誰が見ても正しいことがわかる」そんな仕組みにできたら理想ですね。
そして、私は研究者としてだけでなく、会社の一員としても、自分の知識や経験をチーム全体の力に変えていきたいと思っています。仕組みを整えることで、メンバー一人ひとりが安心して判断できる環境をつくりたいんです。
Sotasは、自由度が高く、アイディアを出せば実現できるイメージが持てるサービス。自分たちのアイディア次第で、どんな形にも進化できる。そう思えること自体が、研究者としてのモチベーションになっています。
一社の誠実が、社会を動かす。―CMPが描く未来へ―
吉元:Sotasは現在、CMP(Chemical Management Platform)の実証にも参画しています。
松尾さん:それもすごく信頼できるポイントです。国のプロジェクトであるCMPにSotasが採択されているのは、まさに信頼の証。
将来、化学品を扱う企業の中で、「Sotasを使っていれば大丈夫」――そう言われるような存在になってほしいです。
そして、私は研究者としてだけでなく、会社の一員としても、自分の知識や経験をチーム全体の力に変えていきたいと思っています。仕組みを整えることで、メンバー一人ひとりが安心して判断できる環境をつくりたい。その積み重ねが、最終的に社会全体の安心につながると信じています。
吉元:まさにそこが、CMPの目指す姿と重なりますね。
CMPは、サプライチェーンを通じて「正しい情報を正しく伝える」ことを目的にしたプロジェクトです。その考え方は、松尾さんが話してくださった“誠実な情報管理”と根っこが同じだと思います。
一社の中で誠実を貫くことが、やがて社会全体の信頼を形づくる。 クボタケミックスさんの取り組みは、まさにその先駆けだと感じています。